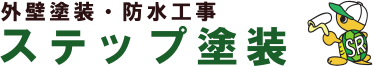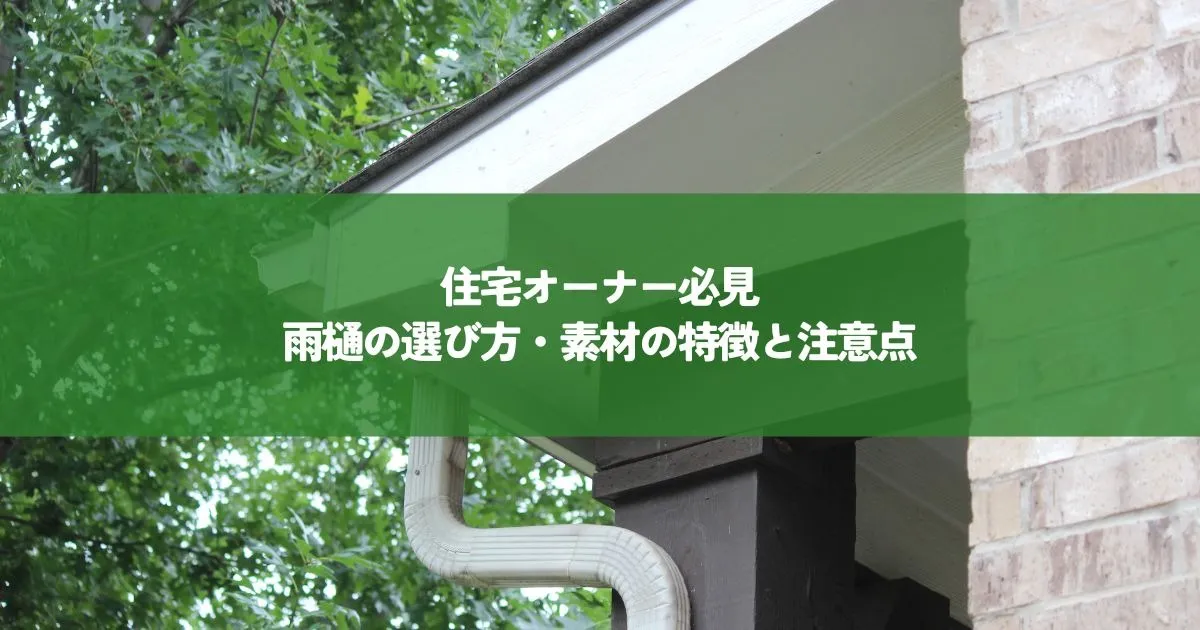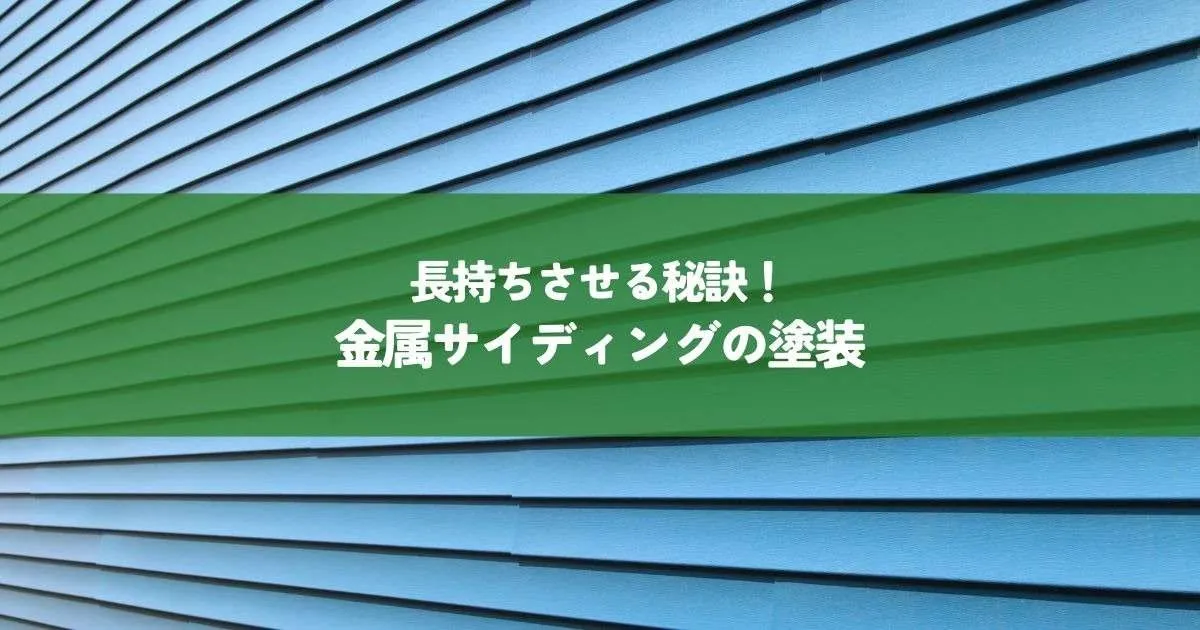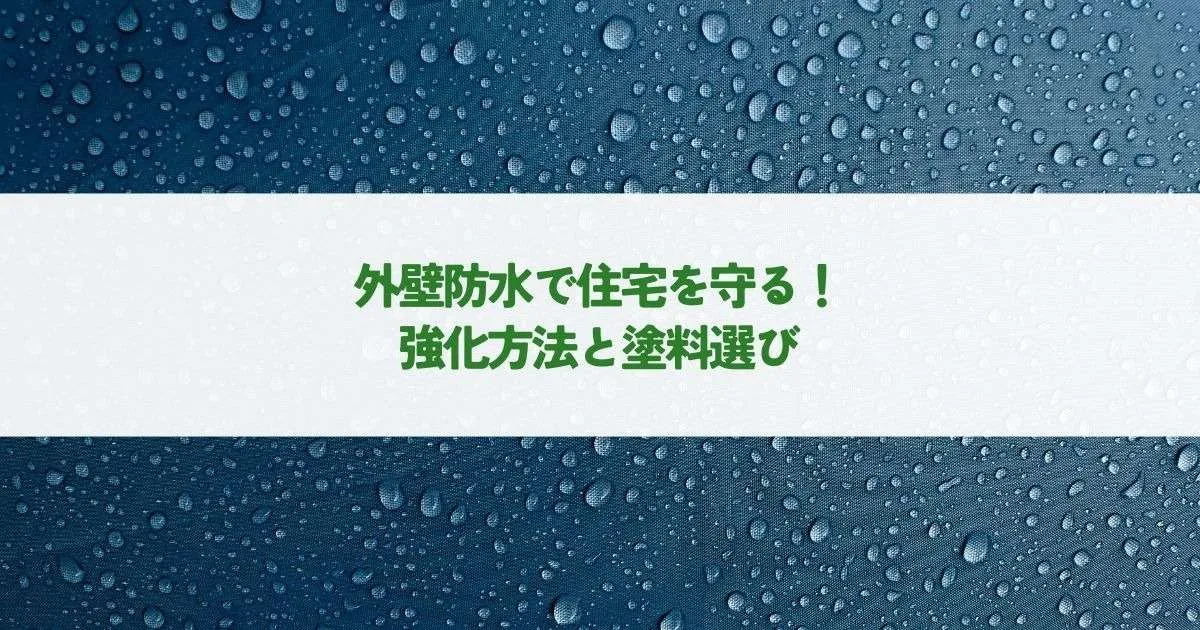住宅オーナー必見!雨樋の選び方・素材の特徴と注意点
2024/06/29
雨樋のサイズ種類と特徴
軒樋のサイズ
軒樋のサイズは、主に幅で表されます。
一般的なサイズは、半円型で75mm、100mm、105mm、120mmなど、角型ではメーカーによって様々です。
半円型はメーカー間でサイズに多少の差はありますが、ほぼ共通しています。
角型はメーカーによって寸法が大きく異なるため、交換時は同じメーカーの製品を選ぶことが重要です。
縦樋のサイズ
縦樋のサイズは、主に直径で表されます。
一般的なサイズは、45mm、55mm、60mm、75mm、90mmなどがあります。
長さも様々で、1800mmや2700mmなどが一般的です。
工場などでは、さらに大きなサイズのものも使用されます。
サイズ表記の見方
軒樋は幅、縦樋は直径でサイズが表記されます。
メーカーによっては、独自のサイズ表記を使用している場合もありますので、製品カタログなどで確認しましょう。
また、製品には型番が刻印されていることが多く、型番を調べることで、サイズや材質などの詳細を確認できます。
雨樋選び方の基礎知識
屋根の形状と雨樋のタイプ
屋根の形状によって、適切な雨樋の種類が異なります。
例えば、勾配屋根には軒樋と縦樋の組み合わせが一般的ですが、平らな屋根では、軒樋のないタイプも存在します。
また、パラペットのある屋根では、内樋を使用するケースもあります。
素材による違いと選び方のポイント
雨樋の素材には、塩ビ、金属(ステンレス、銅、ガルバリウム鋼板)などがあります。
塩ビは安価で加工しやすい一方、紫外線に弱く、経年劣化しやすいです。
金属製は耐久性が高いですが、価格が高く、錆びる可能性もあります。
それぞれの素材の特性を理解し、設置場所や予算などを考慮して選びましょう。
排水能力の重要性
雨樋のサイズは、排水能力に大きく影響します。
屋根の面積や降雨量を考慮し、適切な排水能力を持つ雨樋を選ぶことが重要です。
排水能力が不足すると、雨水が溢れ、外壁や基礎などに被害が及ぶ可能性があります。
雨樋選びで失敗しないためのチェックポイント
必要な排水量を計算する
雨樋の適切なサイズを選ぶためには、屋根への降雨量と雨樋の排水量を比較することが重要です。
屋根の面積と地域の降雨強度から降雨量を計算し、各メーカーが公開している排水能力表や計算ツールなどを用いて、軒樋と縦樋の組み合わせを検討しましょう。
計算には専門的な知識が必要となるため、不安な場合は専門業者に相談することをお勧めします。
専門業者への相談
雨樋のサイズ選びは、専門的な知識が必要なため、自身で判断することが難しい場合があります。
不安な場合は、雨樋の施工経験が豊富な専門業者に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
雨樋の素材の種類と特徴
塩ビ製雨樋
塩ビ製雨樋は、安価で加工が容易なため、多くの住宅で使用されています。
軽量で施工性も良好です。
しかし、紫外線に弱く、経年劣化しやすいという欠点もあります。
金属製雨樋(ステンレス・銅・ガルバリウム鋼板)
金属製雨樋は、塩ビ製に比べて耐久性が高いです。
ステンレスは錆びにくく、銅は経年変化で美しい緑青色になり、ガルバリウム鋼板は耐候性に優れています。
ただし、価格が高いという点に注意が必要です。
FAQよくある質問
Q1. 雨樋の掃除はどのくらいの頻度で行えば良いですか?
A1. 雨樋の掃除は、少なくとも年に1回は行うことをお勧めします。
特に、葉っぱなどが詰まりやすい秋は、こまめな掃除が必要です。
Q2. 雨樋の寿命はどのくらいですか?
A2. 雨樋の寿命は、素材や設置環境によって異なります。
塩ビ製は10~15年、金属製は20年以上とされていますが、適切なメンテナンスを行うことで寿命を延ばすことができます。
Q3. 雨樋の修理・交換費用はどのくらいかかりますか?
A3. 雨樋の修理・交換費用は、使用する素材、工事の規模などによって大きく異なります。
まとめ
今回は、雨樋のサイズの種類、選び方、素材について解説しました。
雨樋は建物を雨から守る重要な役割を担っています。
適切なサイズと素材の雨樋を選ぶことで、雨漏りや建物の劣化を防ぎ、安心安全な生活を送ることができます。
屋根の面積、地域の降雨強度、予算などを考慮し、最適な雨樋を選びましょう。
必要であれば、専門業者に相談することも検討してください。
雨樋の選び方を理解することで、快適な住まいづくりに役立てていただければ幸いです。